
D/Aコンバータ(CXA1315P)
SPECTRUM開発の”反転レベルシフトPLL回路”への応用
この章では、D/AコンバータをPLL周波数の安定性を向上させた(ループフィルタに「ゲタ」を履かせた)反転レベルシフト回路に接続して使うとき必要な制御法を中心に解説します。反転レベルシフトについての詳細は、「秘伝のPLL設計法」の章をご覧ください。まず、D/Aコンバータとはどんなものかを簡単に説明し、GigaStで用いられてきたソニー社製CXA1315PのD/Aコンバータを例にとって解説することにします。
 |
| 図1.GigaStスペアナ(第一世代版)で使用した D/Aコンバータ(CXA1315P) |
(注)第2世代以降のGigaStスペアナでは、回路構成の変更によりD/Aコンバータ(CXA1315P)が使われなくなりました。第一世代からの改造などで不要となった読者の方!この部品をPLL回路に活用してみませんか。また手持ちにD/Aコンバータがない読者の皆さんには、なにもCXA1315でなければならないということはありません。AKI−H8マイコンにはD/Aコンバータが内蔵されています。ですが、新たにD/Aコンバータを選んだり、使用したりするときに必要になりそうな特性の見方なども説明します。ぜひD/Aコンバータの選び方、使い方をマスターしていってください。
![]() 簡単なD/Aコンバータの原理
簡単なD/Aコンバータの原理
D/Aコンバータは、ディジタル量をアナログ量に変換する回路なので、中身はさぞ複雑であろうと思う読者の方も多いかもしれませんが、実はとても簡単なものなのです。
(1)重み抵抗型D/Aコンバータの例
図2に示すような、OPアンプを利用した加算回路を考えてみます。
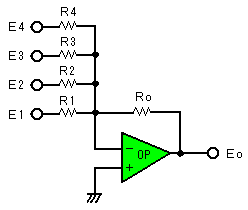 |
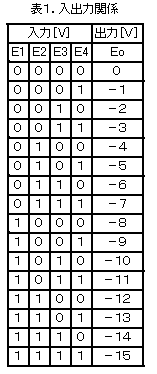 |
| 図2.加算回路 | |
この回路で入力電圧をE1,E2,E3,E4とすると、出力電圧Eoは、
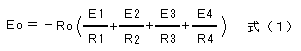
となります。
もし、R2=2×R1,R3=4×R1,R4=8×R1とおくと、
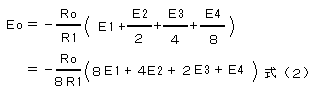
簡単のために、Ro/8R1=1となるようなRo,R1を選ぶと、
Eo=−(8E1+4E2+2E3+E4) 式(3)
となります。
ここで、E1,E2,E3,E4の入力端子に「0V」か「1V」が入った場合に、出力電圧Eoがどのようになるか考えてみます。すなわち、
E1=0V,E2=0V,E3=0V,E4=0V のとき Eo= 0V
E1=0V,E2=0V,E3=0V,E4=1V のとき Eo=−1V
E1=0V,E2=0V,E3=1V,E4=0V のとき Eo=−2V
E1=0V,E2=0V,E3=1V,E4=1V のとき Eo=−3V
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
E1=1V,E2=1V,E3=1V,E4=1V のとき Eo=−15V
これらの関係をまとめると表1のようになります。これは、あるディジタル量に対し、それに対応するアナログ量を出力する回路、つまりD/Aコンバータ(重み抵抗型)になっていることがわかります。この方式で、nビットのD/Aコンバータを作る場合、2n−1R〜Rという広範囲で、精度よく2倍ずつになる抵抗が必要になるため、高精度のD/Aコンバータには不向きですが、部品点数が少なく簡単な用途に向いています。
(2)ラダー抵抗型D/Aコンバータの例
図3に概略回路図を示します。抵抗Rと2Rがはしご(lader)状に構成されていることから、はしご型(ラダー型)D/Aコンバータと言われます。使う抵抗値がRと2Rの2種類だけで構成されるため、高精度で温度特性も良好です。この方式はIC化しやすいため、多くのD/Aコンバータ用ICが採用しています。そういえば、秋月DDSキット(10ビットD/Aコンバータ部)でも使われています。
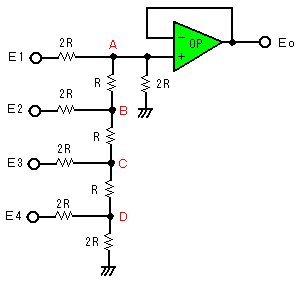 |
| 図3. ラダー抵抗型D/Aコンバータの回路構成例 |
ラダー型抵抗の性質を見てみましょう。ラダー型回路は、図3のA,B,C,Dのどの接続点においても等価的に2Rの抵抗が3方向に接続されているというものです。これを図4のアニメーションを使って説明します。
例えばE1,E2,E3,E4の4ビットが0010に設定されていたとするとE3入力だけが「1」なので、C点における抵抗の接続状態が分かります。
(1)まず、E1=0ですのでE1はGNDに接続されているものと見なされます。
(2)A点での2R抵抗は並列に接続されているためRになります。
(3)B点からA点方向を見るとRが直列に接続されているため2Rになります。
(4)同様にして、E2=0ですのでE2はGNDに接続されているものと見なされ、B点での2R抵抗は並列に接続されているためRになります。
(5)C点からB点方向を見るとRが直列に接続されているため2Rになります。
(6)同様にして、E4=0ですのでE4はGNDに接続されているものと見なされ、D点での2R抵抗は並列に接続されているためRになります。
(7)C点からD点方向を見るとRが直列に接続されているため2Rになります。
(8)E3に電圧Vを加えると、C点に電流 I=V/3Rが流れ、C点でそれぞれ、I/2に分かれます。A,B,D点も同様に見ていくと成り立つことが分かります。
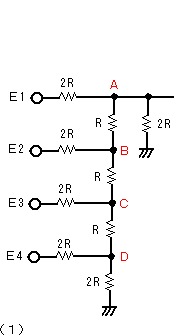 |
| 図4.ラダー型抵抗の性質(アニメーション) |
図5を使って、ラダー抵抗型D/Aコンバータの原理を説明します。
ラダー型抵抗の性質から電流が各接続点で1/2になっていく様子が分かると思います。
(1)ディジタル入力が0010のとき、E3に加えられた電圧Vにより、Eo=(2/24)Vとなります。
(2)ディジタル入力が0100のとき、E2に加えられた電圧Vにより、Eo=(4/24)Vとなります。
以下同様に求めていくと、ディジタル入力値×V/24の関係があることがわかります。
したがって、4ビットのD/Aコンバータの場合には、式(4)のようになります。
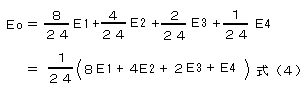
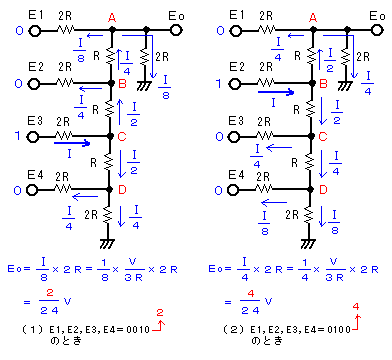 |
| 図5.ラダー抵抗型D/Aコンバータの原理 |
実際のD/Aコンバータでは、周波数特性や温度特性を向上させるような工夫がされていますし、その他にも様々な種類のD/Aコンバータが存在します。
もし興味があれば、CQ出版社からトランジスタ技術SPECIAL 「No.16 A−D/D−A変換回路技術のすべて」をご覧ください。
![]() D/Aコンバータ選択上の注意
D/Aコンバータ選択上の注意
本スペアナでは、ソニー社製CXA1315Pを使用しましたが、いざD/Aコンバータを買ってみようかとすると、どんなD/Aコンバータを選んだらよいか、迷うものです。ここでは、そんなときに役立ちそうなことを書いておきます。
(1)D/Aコンバータの分類
D/Aコンバータを選ぶという立場で分類してみました。
以上、D/Aコンバータを選ぶ立場から、いくつかの分類を行いましたが、よく使用される分類に、「電圧出力タイプ」、「電流出力タイプ」があります。一般的には、電圧出力タイプのD/Aコンバータの方が使いやすく、セトリング時間が短いことが要求される特殊な応用例を除いては、電圧出力タイプのD/Aコンバータでよいと思います。電流出力タイプのD/Aコンバータは、その電流を抵抗に流して電圧を得るなどの使い方が一般的で、高精度の電圧出力を得るのには向きません。ただし、交換に要する時間はかなり速いので、高速性が要求される回路には、よく使われます。また、一般的に、電流出力タイプの方が安価な場合が多いので、ちょっとした試作などには、電流出力タイプのD/Aコンバータがよく用いられます。
(2)D/Aコンバータを選ぶときの注意
それでは、D/Aコンバータを使用した回路を作るとき、実際にどのD/Aコンバータを選べばよいのでしょうか。それには次の手順で選ぶと、割と選びやすいと思います。
以上、D/Aコンバータを選ぶときに役立ちそうなことを書いておきました。実際には規格表をみて必要な項目をチェックし、少し高めの価格のものを選べば間違いはないでしょうが(^^;)、狭帯域版スペアナのPLL回路のゲタ電圧に使うのであれば、さほど高い分解能と速度は必要ありませんので、選択の幅はそれほど狭くはないと思います。
![]() D/Aコンバータ(CXA1315)についての解説
D/Aコンバータ(CXA1315)についての解説
本スペアナのD/Aコンバータでは、ソニー社製CXA1315Pを取り上げ、その使い方の紹介をします。CXA1315Pの外観を図1に示します。このD/Aコンバータのピン配置は、図6のようになっていて16ピンのDIPタイプです。CXA1315は、I2C BUS対応の8bit 5ch D/Aコンバータとして開発されたICです。表2にピンの機能をまとめてみました。
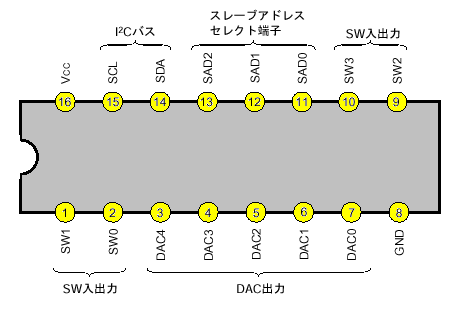 |
| 図6.ソニー社製D/Aコンバータ(CXA1315)のピン配置図 |
CXA1315の特長
ここで、I2Cという言葉が出てきましたが、Inter−Integrated Circuit の頭文字から由来しています。この方式は、フィリップス社が提唱したもので、2本の接続線で1個のマスターに対し複数のスレーブとの間でパーティラインを構成し、最大400kbpsの通信が可能となっています。D/Aコンバータ以外にも、A/Dコンバータ、EEPROM、表示制御デバイスなどで、I2Cインターフェースを内蔵した製品が各社から発売されています。I2Cの特徴は、ここのスレーブがアドレスを持っていて、データの中にアドレスが含まれていることと、1バイト転送ごとに受信側からACK信号の返送をして、互いに確認をとりながらデータ転送を行っていることです。
フィリップス社のI2Cの英文の仕様書は、下記からダウンロードできます。
http://www-us.semiconductors.philips.com/i2c/facts/#speciication
| ピンNo | 名称 | 機能 |
| 1 | SW1 | 汎用 I /O ポートの入出力端子 |
| 2 | SW0 | 汎用 I /O ポートの入出力端子 |
| 3 | DAC4 | D /A コンバータ出力端子 |
| 4 | DAC3 | D /A コンバータ出力端子 |
| 5 | DAC2 | D /A コンバータ出力端子 |
| 6 | DAC1 | D /A コンバータ出力端子 |
| 7 | DAC0 | D /A コンバータ出力端子 |
| 8 | GND | GND 端子 |
| 9 | SW2 | 汎用 I /O ポートの入出力端子 |
| 10 | SW3 | 汎用 I /O ポートの入出力端子 |
| 11 | SAD0 | スレーブアドレスの入力端子 |
| 12 | SAD1 | スレーブアドレスの入力端子 |
| 13 | SAD2 | スレーブアドレスの入力端子 |
| 14 | SDA | I 2C BUS のSDA 入出力端子 |
| 15 | SCL | I 2C bus のSCL 入力端子 |
| 16 | VCC | 電源端子 |
![]() シリアルデータの設定法について
シリアルデータの設定法について
CXA1315は、I 2C BUS によるシリアルコントロールで、SDA (Serial
Data ),SCL (Serial Clock )の2 本の信号があります。SDA
は双方向で、図7のようにH,L,Hi-Z の3値出力をとります。
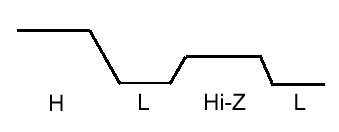 |
| 図7.SDAの3値出力レベル |
I 2C通信の流れを簡単に説明すると、図8のようになります。
(1)クロック(SCL)がhighのときに、データ(SDA)が立ち下がると通信スタート
すなわち、Start Condition 「S」の状態
(2)クロック(SCL)がlowになるごとに順次1ビットずつデータそのものを送信していく。
(3)クロック(SCL)がhighのときに、データ(SDA)が立ち上がると通信ストップ
すなわち、Stop Condition「P」 の状態
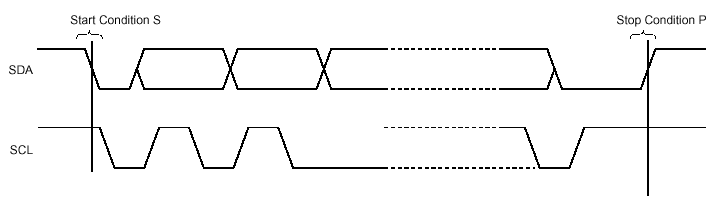 |
| 図8. I2C転送のタイミングチャート |
図9に、I2Cデータの書き込み時のタイミングチャートを示します。横に長くなるため、3段に分けて掲載しています。まず、Start
Condition「S」を出力し、続いてAddress(スレーブアドレス)とRead/Write要求を入力します。Read/Write要求では、書き込み時の場合は[L]です。スレーブアドレスの構成については図10に示します。セットされたアドレスと一致したデバイスだけがその後のデータを受け取り動作します。
つまり、図6のピン配置図でSAD2,SAD1,SAD0端子がありますが、これらの端子を例えばGNDに接続したならば、SAD2=[L],SAD1=[L],SAD0=[L]となります。また、電源端子に接続したならば、SAD2=[H],SAD1=[H],SAD0=[H]となります。Addressが完了すると自動的にデバイスは、ACKビット(Hi−Z)を返送します。
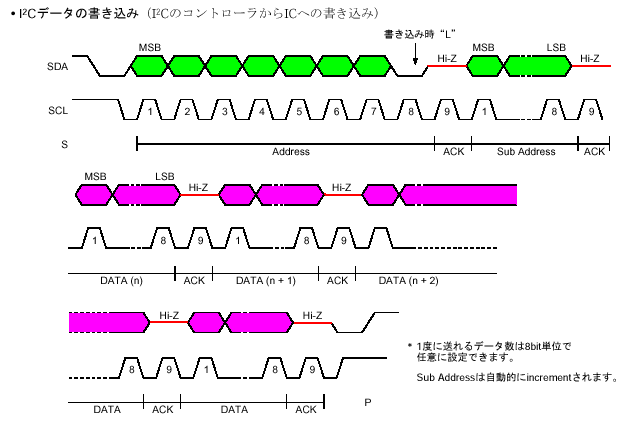 |
| 図9. I2Cデータの書き込み時のタイミングチャート |
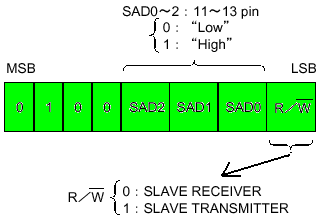 |
| 図10. I 2C Bus レジスタの定義<スレーブアドレス> |
次に、SubAddressを入れます。表3にレジスタ表を示します。DAC0へ出力をするならば、サブアドレスは[xxxxx001]ですが、Xは[0]でも[1]でもよいため、ここでは例えば[00000001]としておきます。このあとは、指定された方向でD/Aコンバータのディジタルデータ入力値を送ります。サブアドレスは、オートインクリメントされていきますので、順にデータを入力すればDAC0〜4まで設定できます。データそのものの通信では、SCLのクロックに従って順次8ビットのデータを入力し、デバイス側が受信の完了を確認するとアクノリッジ(ACK)信号を返送します。最後のデータを送り終わり、ACKの返送後、SDAをLowにしてクロックを停止してHighにしてから、SDAをHighにすることで、Stop
Condition「P」 の状態となり、通信が完了します。これが基本の転送手順です。
| 表3. レジスタ表 |
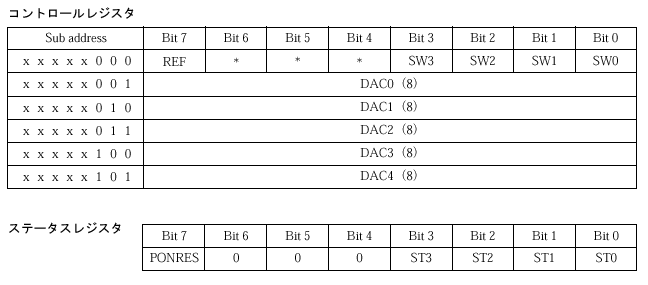 |
<レジスタ説明>()内はbit 数
PLL回路で使用するときには、D/Aコンバータはデータの読み込みはしませんが、図11に参考のためI2Cデータの読み込みのタイミングチャートを掲載しておきます。
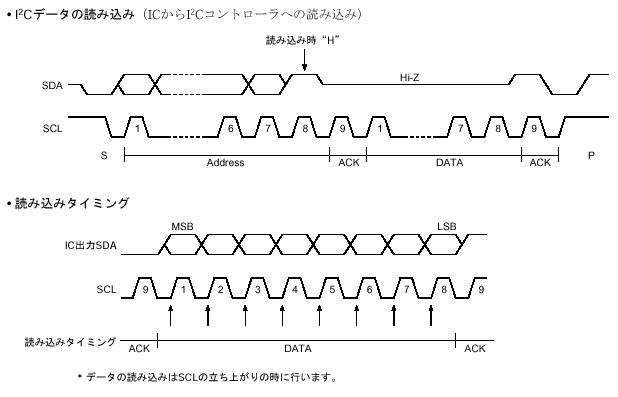 |
| 図11. I2Cデータの読み込み時のタイミングチャート |
![]() 反転レベルシフトPLL回路への応用上の注意点
反転レベルシフトPLL回路への応用上の注意点
(1)CXA1315の電源電圧について
電源電圧範囲ですが、8.2V〜9.8Vです。絶対最大定格は12Vですので、9V程度の電源が必要です。
(2)ゲタ電圧の設定について
図12の加算器の非反転端子側に入力される「ゲタ電圧」ですが、POSシリーズのVCOと組み合わせて使う場合には、なるべく周波数範囲を広くとるために、コントロール電圧を20Vまで必要とします。CXA1315の出力電圧範囲は、0.4V〜8.5V(TYP)となっています。したがって8.5Vを20Vまで、すなわち20/8.5=約2.35倍に拡大(増幅)することになります。図12のOP3でD/A変換出力を増幅しますが、このときのRA,RBの抵抗値を求めてみましょう。OP2の加算器側で2倍の増幅度がありますので、OP3側では2.35/2=約1.18倍にする必要があります。(1+RB/RA)=1.18より、RA=10kΩとすると、RB=1.8kΩになります。
ただし、反転レベルシフトですので、MB1501のチャージポンプの電圧分(約1V〜3V)が差し引かれますので、20V+αで少し出力電圧範囲に余裕を持たせた方がよいでしょう。(あまり高いと、VCOのコントロール電圧の耐圧をオーバーするので注意)
RB=1.8kΩ+数100Ωの半固定可変抵抗を接続しておきます。半固定可変抵抗の接続位置ですが、なるべくRBとOP3の出力端子側に直列接続します。非反転端子側は、比較的インピーダンスが高くなりますので、ノイズの影響を受けないようになるべく短く配線します。
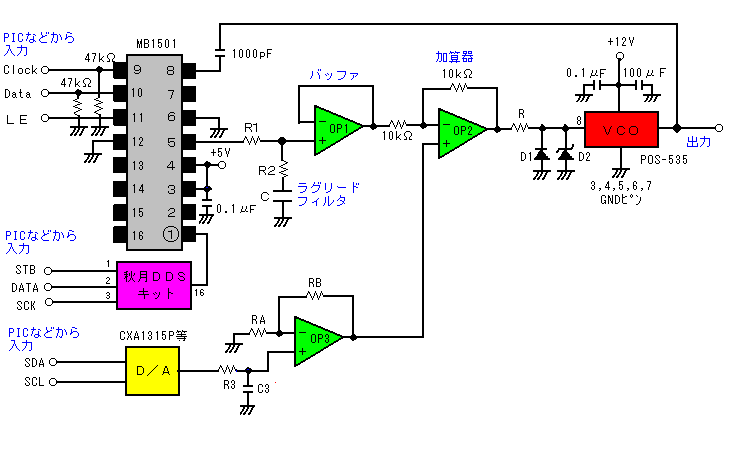 |
|
| 図12.DDS&反転レベルシフトPLL回路図 |
(3)チューニング電圧の設定ノウハウ
図13にPOS−535のチューニング電圧に対する出力周波数特性を示します。例えば、500MHzの周波数では、チューニング電圧は約12Vになっています。ここで、D/Aコンバータの出力電圧との関係を求めますが、反転レベルシフトですので、MB1501のチャージポンプの電圧分(約1V〜3V)を+αしておきます。α=2Vと設定するならば、ゲタ電圧は、12+2=14Vになります。前項で求めたようにD/A変換出力電圧を約2.35倍とすると、14/2.35=約6VにD/A変換出力を設定します。同様に300MHzの周波数では、チューニング電圧は約2Vですので、ゲタ電圧は2+α=4Vとなり、4/2.35=約1.7Vに設定します。
さて、図13を見るように、チューニング電圧に対する出力周波数特性は、厳密には直線的ではありません。したがって、D/Aコンバータの出力電圧もその特性に合わせて、それぞれ設定していかなくては・・・と思われる前にノウハウを公開しておきます。レベルシフト法は、D/Aコンバータの出力電圧と出力周波数特性の関係を直線的に設定できるのです。非直線部分は、MB1501のチャージポンプ電圧が+α分を自動的に調節してくれるのです。
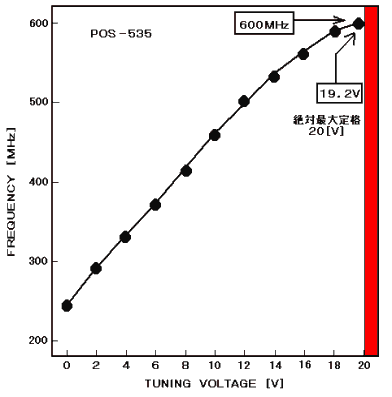 |
| 図13.POS−535 チューニング電圧に対する出力周波数特性 |
 |